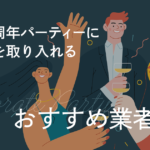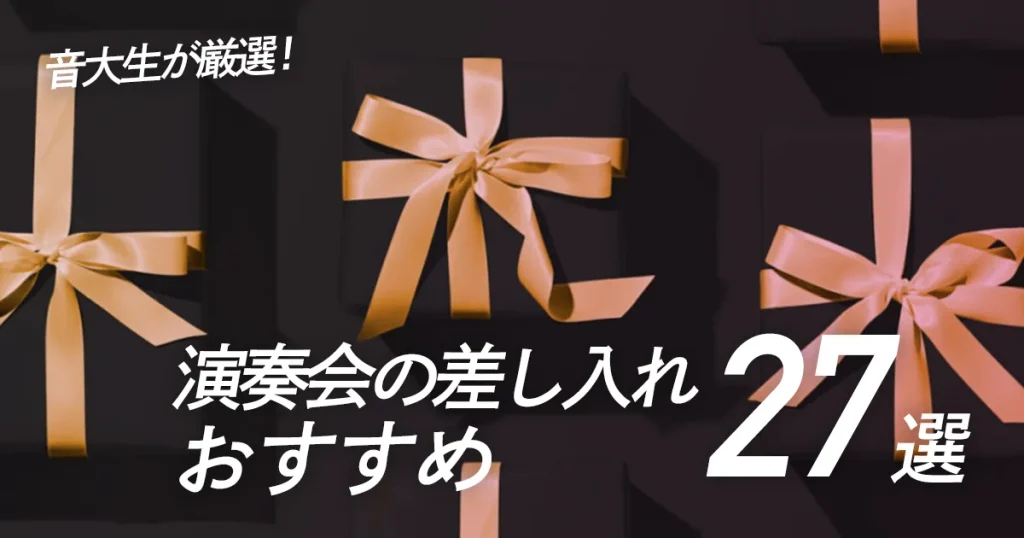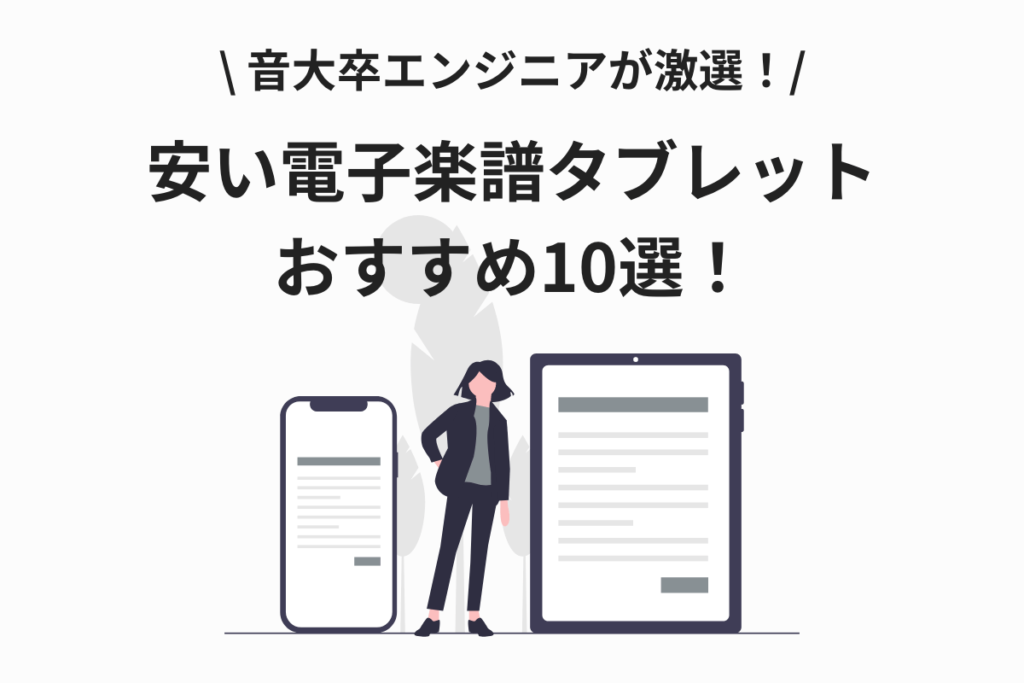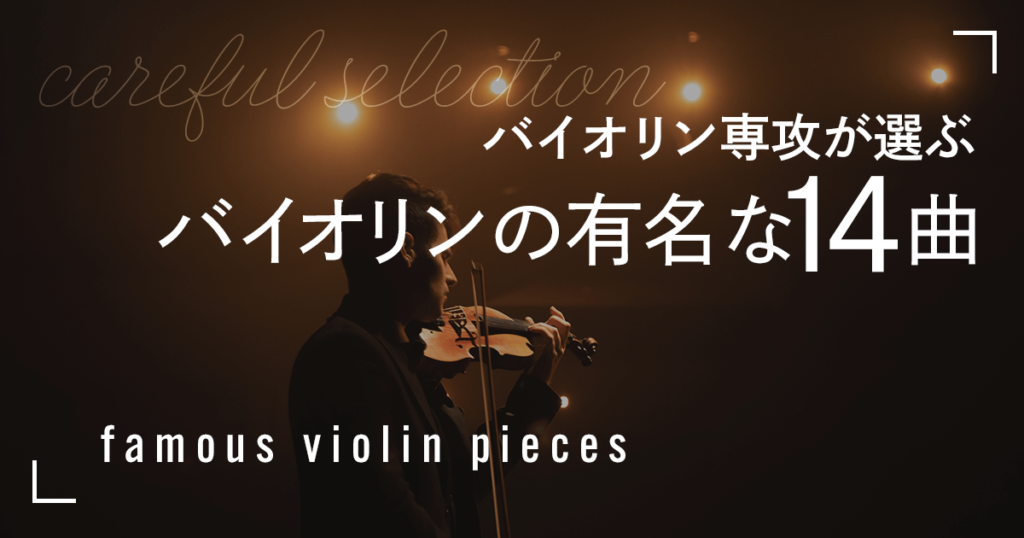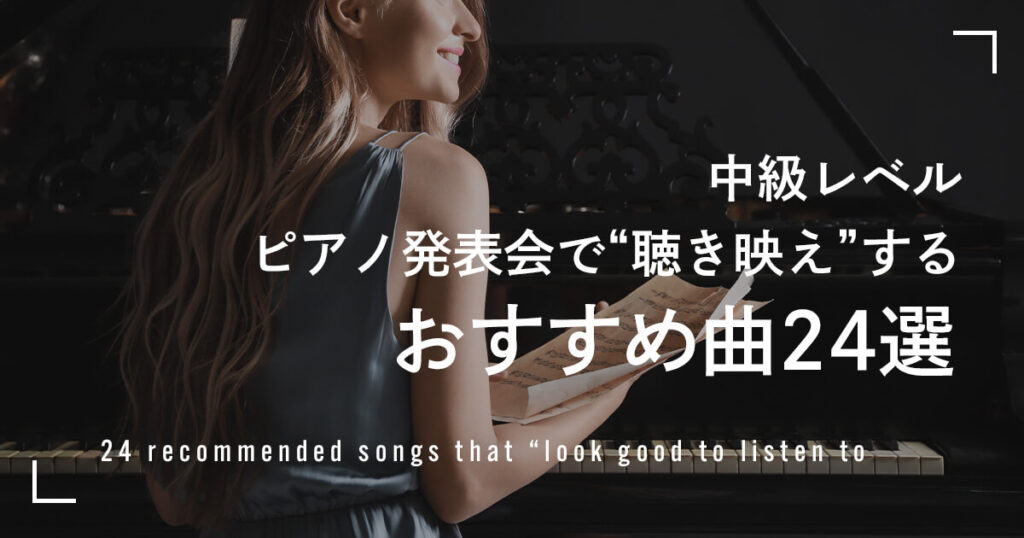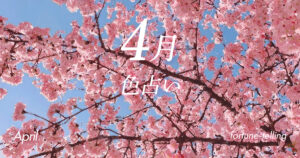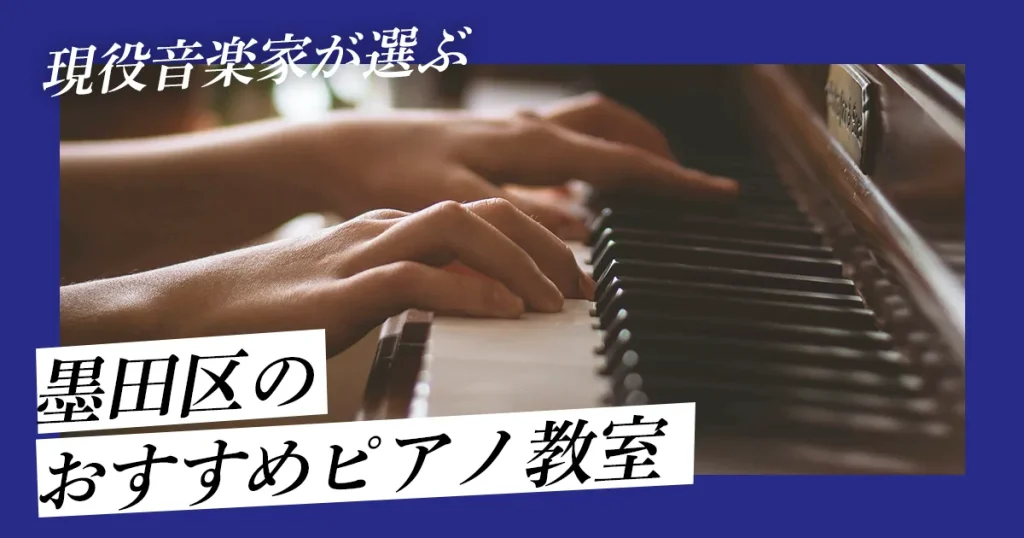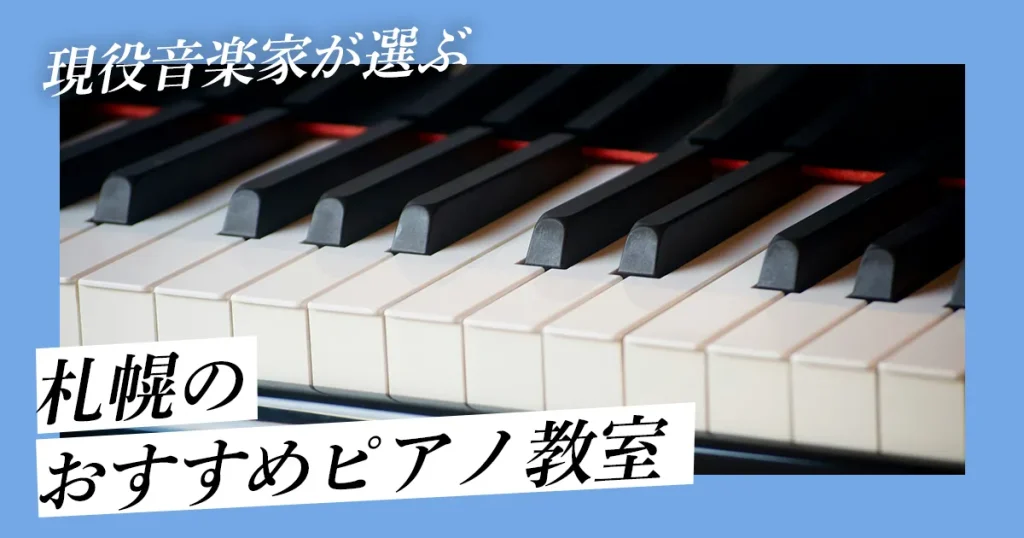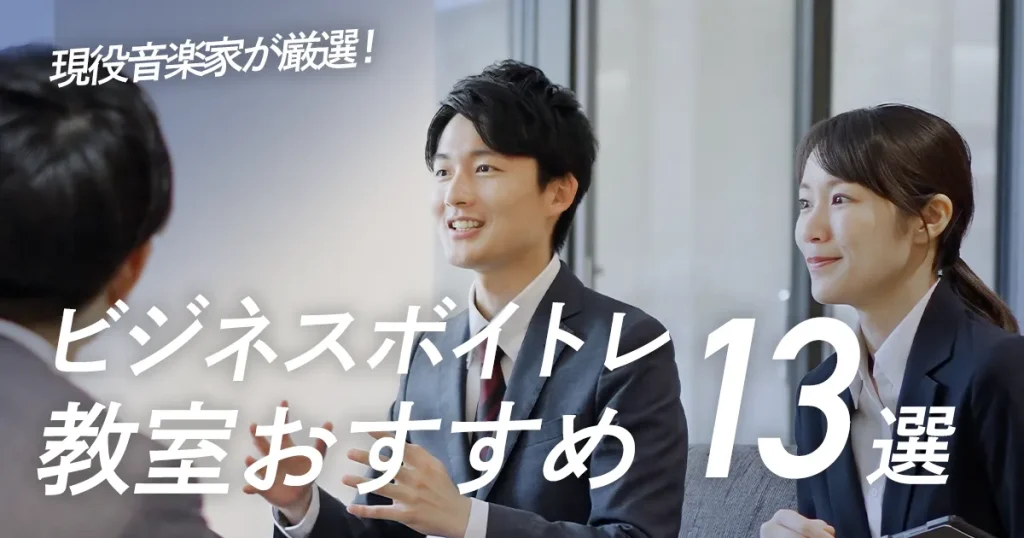イベントのクオリティを高めるために生演奏を呼びたいけれど、予算が厳しくて……
そんなとき、「無料で依頼できないだろうか?」と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、無料で演奏を依頼できるケースは非常に限られています。
本記事では、音大卒ライターがボランティア演奏とプロ演奏の違いをわかりやすく整理し、限られた予算の中で最適な演奏家を見つける方法まで丁寧に解説します。
目次
“無料で演奏依頼”はどこまで可能か?

演奏依頼が「無料」になる代表的な 4シチュエーションをご紹介します。
アマチュア奏者にボランティア演奏をお願いする
地域アマチュア楽団や趣味サークルは「人前で演奏できる場」を探しています。
謝礼なしでも引き受けてもらえることがありますが、演奏水準は個人差が大きく、当日キャンセルのリスクも高めです。
観客参加型の温かな雰囲気を重視するイベントであれば十分に選択肢になります。
教育プログラムの一環(音大・音高の実習)
音大生が授業単位取得や実技経験を目的として、公共施設や学校、福祉施設で演奏する場合は、無料での依頼が認められることもあります。
ただし、私自身、音大生時代に福祉施設で演奏した際にはしっかりと謝礼をいただいた経験があるため、最終的には学校側との相談内容によって変わってきますね。
地域・行政の助成イベント
自治体の文化芸術推進事業では、演奏者の謝礼を助成金でまかなう制度が整っています。
審査に通れば助成金が出ます。しかし申請書類の作成と報告書の提出が発生し、採択まで1〜3か月かかる点を見込んでおきましょう。
プロモーション目的のボランティア演奏
プロの演奏者がCD発売やリサイタルのPRを目的に、「露出機会」を報酬として受け入れるケースも稀にあります。
その際は、演奏家に対してSNS投稿やチラシ配布などの宣伝協力を条件とすることが一般的です。
とはいえ、音楽を職業とする演奏家に無料で依頼するのは、基本的に難しいと考えておくほうがよいでしょう。
演奏依頼 無料でも発生しやすい隠れコスト

無料で演奏依頼ができたとしても、以下のコストは依頼者が負担する必要があります。
| 項目 | 内容例 |
|---|---|
| 交通費・搬入費 | 大型楽器は必須。新幹線移動なら数万円。 |
| 機材レンタル費 | マイク・ミキサー・PAスピーカーの手配。 |
| 控室・食事 | 長時間拘束の場合、弁当や待機場所を用意。 |
| 著作権使用料 | 有料イベントや録画配信時はJASRAC申請が必要。 |
ボランティア演奏とプロ演奏の違い
ボランティア演奏とプロ演奏の違いは以下になります。
| 比較項目 | ボランティア演奏 | プロ演奏 |
|---|---|---|
| 技術・表現力 | 初心者〜アマ上級者でバラつき大 | 専門教育+現場経験で安定したクオリティ |
| リハーサル対応 | 当日短時間のみが多い | 事前打合せ・編曲対応・細部調整が可能 |
| 効果 | 親しみや温かみを演出 | 高級感・信頼・集客力を向上 |
| キャンセルリスク | 高い(代役確保は依頼者側) | 低い(事務所や仲介が代演を手配) |
| 費用目安 | 無料〜1万円+実費 | 1.5万円〜/人(拘束時間・編成で変動) |
プロ演奏者に演奏依頼するメリット4選

ここまで読んでいただいて、「ボランティア演奏の方がお得!」と感じる方も多いと思います。
ですが、多少費用がかかりますがプロの演奏者に演奏依頼するメリットはたくさんあります。
演奏レベル・パフォーマンス能力が高い
プロ奏者は音楽大学や専門機関で鍛えた確かな技術に加え、数々の本番をくぐり抜けてきた経験があります。
繊細な表現も安定して再現できたり、突発的なトラブルにも臨機応変に対応ができます。
「外さないクオリティ」を担保できるので、企業レセプションや高価格帯のブライダルなど、失敗が許されないシーンでも安心して任せられます。
演出の幅を広げられる
編成変更・メドレー制作・キー変更といった楽曲アレンジはもちろん、歌やダンスとのコラボ、ゲスト参加型のワークショップまで、プロは演奏そのものを“演出素材”として自在にカスタマイズできます。
サプライズ演奏や物語仕立てのステージなど、動画映え・SNS映えする仕掛けを提案してくれるため、イベントコンテンツの差別化が容易です。
集客・PR 効果が高い
コンクールの受賞歴やメディア出演実績がある演奏者は、それだけで注目度が高まります。
加えて、日頃からSNSで情報発信を行いフォロワーを多く抱えている方も多いため、演奏者自身のファン層をイベントに呼び込むことで新規顧客の獲得につながります。
継続依頼しやすい
プロ奏者は音楽を本業とするプロフェッショナル。そのため、平日・休日を問わずスケジュール調整がしやすく、毎回スムーズに依頼を進められます。
一方、ボランティア演奏者は本業が別にある場合が多く、予定が合わず依頼しづらいこともあります。
さらにプロは演奏クオリティにムラがなく、シリーズ公演や定期イベントでも安心して“リピート”できる点が大きな強みです。
同じ奏者を継続的に起用すれば固定ファンがつきやすく、イベントの一貫性と顧客エンゲージメント向上にもつながります。
“予算に合わせて”演奏家を探す方法

「音楽事務所に頼むと予算オーバーしそう…」「プロ奏者への連絡方法がわからない…」
そんなお悩みをお持ちの方には、SHARE MUSICA(シェアムジカ)がおすすめです。
SHARE MUSICA(シェアムジカ)は現役音楽家による厳格な審査を通過した、実力派音楽家のみが登録できる演奏依頼マッチングプラットフォームです。
- 月額固定費ゼロ・完全成果報酬制(マッチング成立時のみ手数料)だから、予算に制限のある小規模イベントにも導入しやすい!
- 0円~ご希望の予算内で演奏者を募集・依頼可能。
- 東京藝術大学・桐朋音楽大学・海外大学院修了などの多彩なキャリアを持つプロが多数在籍。
| 演奏依頼料金 | 0円〜自由に設定できる 演奏依頼料金 × 20%の手数料が必要 |
| 運営サポート | スムーズに導入・活用ができるように、 演奏経験のあるスタッフが丁寧にサポート |
| 演奏者との連絡 | メッセージ機能で演奏者と気軽に連絡が取れる |
| 演奏者レベル | 音大在学・音大卒 |
| 日程調整 | 演奏者と交渉し日程調整が可能 (3日前までキャンセル無料) |
一度登録すれば、プラットフォーム上で気になる演奏家と直接チャットでき、条件交渉から手続きまで完結します。
プロへの依頼がぐっと身近になるSHARE MUSICAを、ぜひご活用ください!
まとめ|コストとクオリティのベストバランスを実現しよう
- 完全無料で演奏家を呼ぶことは不可能ではありませんが、
- 無償実習や助成金を活用する
- 宣伝協力など“非金銭報酬”を提示する といった 具体的条件の提示 が不可欠です。
- ボランティア演奏は温かみの演出に最適ですが、演奏の質や集客効果を重視する場面では プロ演奏 が安心。
- SHARE MUSICA を利用すれば予算に合った演奏者を見つけやすい
当ブログでは現役音大生や音大出身のライターが、「音楽に関する質の高い情報」を発信しています。
ぜひ他の記事もご覧いただき、役立てていただければ幸いです。